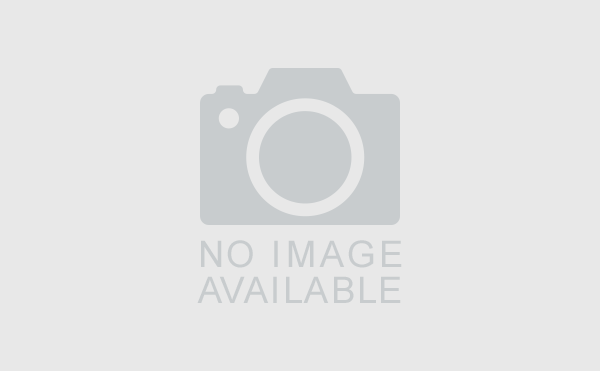二宮町定例議会を傍聴して
去る2月末から始まった二宮町議会は3月21日に最終日を迎え、令和7年度予算が賛成多数により可決されました。
㋂4日に行われた総括質問の内、一石ひろ子議員の質問の一部を紹介します。
重層的課題を抱える町民のセーフティーネットの強化について質問。
生活困窮者自立支援法に繋がる参加型支援を実践し治療中心の引きこもり施策を大きく展開し成果を出した秋田県秋田県藤里町の社会福祉協議会の動きを例に挙げ、二宮町の現状から参加型支援の重要性を求めた。社協、行政、さらに地域住民を含め、個々の可能性が活かされる風土が重要。
二宮町内では町民の間でボトムアップの多様な動きが育ってきている。不登校児童生徒の居場所作り、オーガニック給食稼働の為の農業者をつなぐマネージメントや、環境再生ネイチャーポジティブの動きなど、この町だけでなく広域でモデルとなるチャレンジが生まれているが、個人の努力だけでは限界がある。国はグリーンインフラや流域治水の取り組みなどにもコーディネーターを派遣する仕組みの利用の可能性を求めた。
施政方針の中で、二宮、大磯、中井町、秦野市が繋がる流域治水会議は行政レベルで内水ハザードマップなどの整備に係る標準化に向けて動いているということだが、二宮町では気候非常事態宣言発出、気候市民会議開催など社会資源が充実しており、流域治水を啓発するイベントの共同開催の考えは? 又、国内で多くの被害事例のある2級河川におけ域治水の共同会議の必要性も求めた。
教育については、新しい学びの多様化学校が鎌倉市で生まれ、不登校の児童生徒も多く受け入れているオルタナテイブ校は全国に広がっている。二宮町での施設一体型小中一貫校設置検討会の報告を待ちたい。
その他、観光協会法人化による創造的な展開の見通しについて、常識にとらわれない仕組みとイノベーション、さらに生活文化の創造を担うことを期待したい。
最後に新庁舎、生涯学習センター整備における町長のビジョンについて問うた。